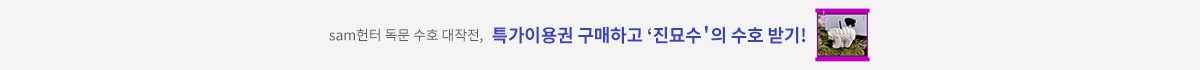- 영문명
- 발행기관
- 일본어문학회
- 저자명
- 黃圭三
- 간행물 정보
- 『일본어문학』日本語文學 第68輯, 329~350쪽, 전체 22쪽
- 주제분류
- 어문학 > 일본어와문학
- 파일형태
- 발행일자
- 2015.02.28

국문 초록
영문 초록
『江戸笑話集』に表われているオノマトペの表記は反復の長い音節で作ら れた語彙が多いが、これは表記に変化を与え、表現効果を狙って考案されたものと考えられる。表記にも平仮名表記、「片仮名+平仮名」の混合表記と反復形の表記がそのまま記録されているのは視覚的な要素ㆍ聴覚的な要素ㆍ口語的な要素を積極的に反映した結果と考えられる。また、当時、表記の側面ではまだ不安定の状態であった半濁音の語頭「パ行音」を用いて、実際日常生活の中で使っていた「パ行音」の生動感のあるオノマトペを活用して一層表現効果を表わしている。
なお、語音結合型は「ABAB型」の語基「AB」に促音「ッ」と撥音「ン」と同じ く、接尾語的な造語成分である「リ」を添加して用いられた型が多様に使われた。当時、「ABッ型」と「ABン型」はほとんど用いられなかったが、現代語では多く使われる型であり、「ABリ型」は反復形である「ABリABリ型」と共に笑話集に多く用いられた。語基「AB」に「り」を添加すれば大体のオノマトペとして役割を充実に履行するようになり、接尾語的な造語成分として有用な語であり、口語的な表現を生々しく記録しようとした笑話集には非常に適合する形態と考えられる。
『江戸笑話集』に用いられた「オノマトペ語基+めくㆍつく」型は、オノマトペ語基の状態表現と動詞化接尾語「-めくㆍつく」の機能が結び付いて、本来の意味をそのまま生かしながら動詞として整然たる意味分担の機能を果たしている。この型は細かく区別できない状態の表現部分をオノマトペが補うという点では非常に有効な言葉である。
목차
일어요약
1. 들어가기
2. 先行研究의 概観
3. 『江戸笑話集』에 나타난 오노마토피아
4. 나오기
参考文献
해당간행물 수록 논문
참고문헌
최근 이용한 논문
교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!

신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.
바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)
지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!